- トップページ
- 虎の巻
知ればもっと好きになる!?お寿司「虎ノ巻」

寿司の歴史をさかのぼれば1千年以上も昔、奈良時代といわれていますが、今の私たちが食べている握り寿司、いわゆる「江戸前寿司」は江戸時代の後期、文化年間(19世紀初め)ごろといいます。気の短い江戸っ子が小腹の空いたとき、気軽に手早く食べられることから大人気になりました。
初期のころはよしず張りの屋台で商われていたそうで、今風にいえばファーストフードといった感じでしょうか。
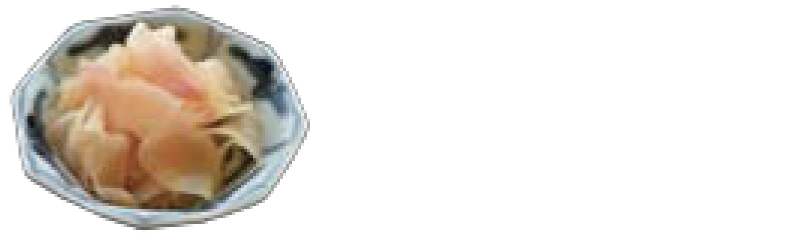
寿司の付け合せに欠かせないガリ。ショウガを薄く切って甘酢漬けにしたものです。それだけ食べても美味しいですが、食通に言わせれば、ガリを食べるタイミングが大事とか。寿司を一貫食べた後に少しのガリをつまむと、舌が新鮮になって次の一貫がより美味くなるそうです。醤油につけたガリをネタの上に乗せて食べる、というのもお勧めだそうです。

寿司は、「江戸の時代から手づかみで食べるものと相場が決まっている」とよく言われます。
その一方で、箸でつまんで食べる人も多くいて、どちらが正しいのでしょうか?その答えは「その人にとって食べやすいのであればどちらも正しい」とか。あたりまえの話ですが…。

「妖術と いう身で握る 鮓(すし)の飯」
という江戸時代の川柳(『柳多留』)があります。寿司職人の技があまりにも見事で、まるで妖術だと江戸っ子を驚かせたのでしょう。握り寿司を創案したのは「興兵衛鮓」華屋興兵衛とも、「松の鮨(通称、本来の屋号はいさご鮨)」堺屋松五郎ともいわれています。舌だけでなく目でも味わえ、楽しめるのが寿司の魅力の一つですね。